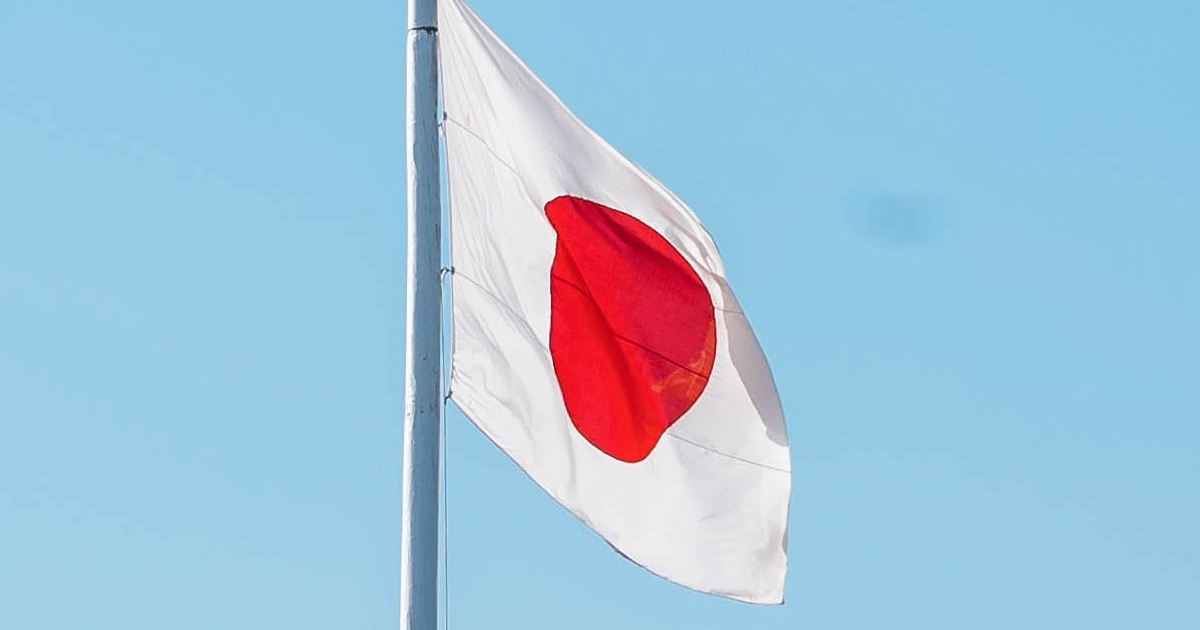脱・西欧史観—国際的通称変更運動を提起する
日本の国号の国際的な通称は、英語である「JAPAN」である。パスポートの表紙にも「JAPAN」と書かれており、五輪などの国際試合における日本代表も「~JAPAN」である。
一方で、日本の国名をそのままローマ字とした「NIPPON」は、紙幣(日本銀行券)や切手等で見られるが、これらは国内向けで使用されるものだ。対外的な表記においては圧倒的に「JAPAN」が多い。
これは何故なのか…と、疑問に思わない人は多いだろう。外国は「JAPAN]と呼ぶから、そのまま受け入れていた…という人がほとんどだ。
だが戦前、一度だけ「NIPPON」が日本の国際的国号として登場した事があった。
明治四十五(一九一二)年五月五日に開幕したストックホルム五輪は、日本が最初に参加した夏季五輪大会である。この時の開会式ではマラソンの金栗四三選手が「NIPPON」と書かれたプラカードを掲げ、堂々と行進した。
ストックホルム大会では、本来「JAPAN」の表記になる予定であったが、大会直前になり、日本選手団の団長であった嘉納治五郎翁が「NIPPON」を掲げる事を急遽決定した。
五輪の歴史の中で日本代表団が「NIPPON」という表記で登場したのはこれが唯一である。
外国人が日本を表現する時に「JAPAN」と呼ぶのは仕方ない事だとしても、日本人がそれに合わせて「JAPAN」を使うのはやはりおかしい。まして、「JAP」は英語圏における日本人の侮蔑的表現だ。嘉納翁はそういう認識から「NIPPON」を掲げる事を決定したのだろう。
大航海時代の慣習を払拭せよ!
この「JAPAN」という表現だが、歴史的にはいつから使用されているのだろうか?
マルコ・ポーロが「東方見聞録」で紹介した「黄金の国ジパング(ZIPANGU)」から来ている、という説が有名だが、定かとは言えない。
十六世紀に書かれたポルトガル人の歴史書では、JAMPON、JAPONGOS、JAPOES、JAPAMなる表記が見られる。東アジアに進出したポルトガル人が、広東語から日本の事を聞いて記録した…という学説もある。
ポルトガル人がアジアに進出した十六世紀は、世界史的には「大航海時代」だが、アジア・アフリカから見れば「西欧列強の侵略」でしかない。地球儀を眺めれば分かるが、アジア、アフリカ、中南米の地名の多くは西欧人が名付けたものだ。日本を「JAPAN」と呼ぶのも、西欧人からの一方的な見方でしかない。
だが近年、そうした欧米中心史観がアジア・アフリカなどのグローバルサウス諸国で「見直し」されている。
特に顕著なのはインドである。インドの都市の地名は英国統治時代に名付けられたものであったが、近年になり、コルカタ(旧カルカッタ)、ムンバイ(旧ボンベイ)、チェンナイ(旧マドラス)と変更がされてきた。
九月に同国で開催されたG20サミットでは、議長国となったインドが「バーラト」なる国名を掲げて、「インドが国名を変更?」と話題になった。
「バーラト」とは古代サンスクリットにおける英雄の名前であり、ヒンドゥー復古主義を唱えるモディ首相は以前より祖国の事を「バーラト」と呼んでいた。
ちなみに「インド」の語源は、インダス川の古名「シンド(大河の意)」から来ている。これをペルシャ人は「ヒンドゥー」と呼び、十六世紀に来航したポルトガル人が、ペルシャ語から「インド」の名を欧州に広めた…と言われる。
インドの国際社会における発言力は徐々に増しているが、今後、国名変更は現実味を帯びて来るかもしれない。西欧侵略史の過程で押し付けられた名称を変更するのもまた、民族主義の表れと言える。
ならば、日本もこれに倣い、国際的な国号を、「JAPAN」「NIPPON」と併記すべきではないだろうか。
国際試合で活躍する選手らを「~ジャパン」と呼ぶのも何か違和感がある。日本の選手はやはり、「がんばれ、ニッポン!」と応援するのが正統の姿ではないだろうか。