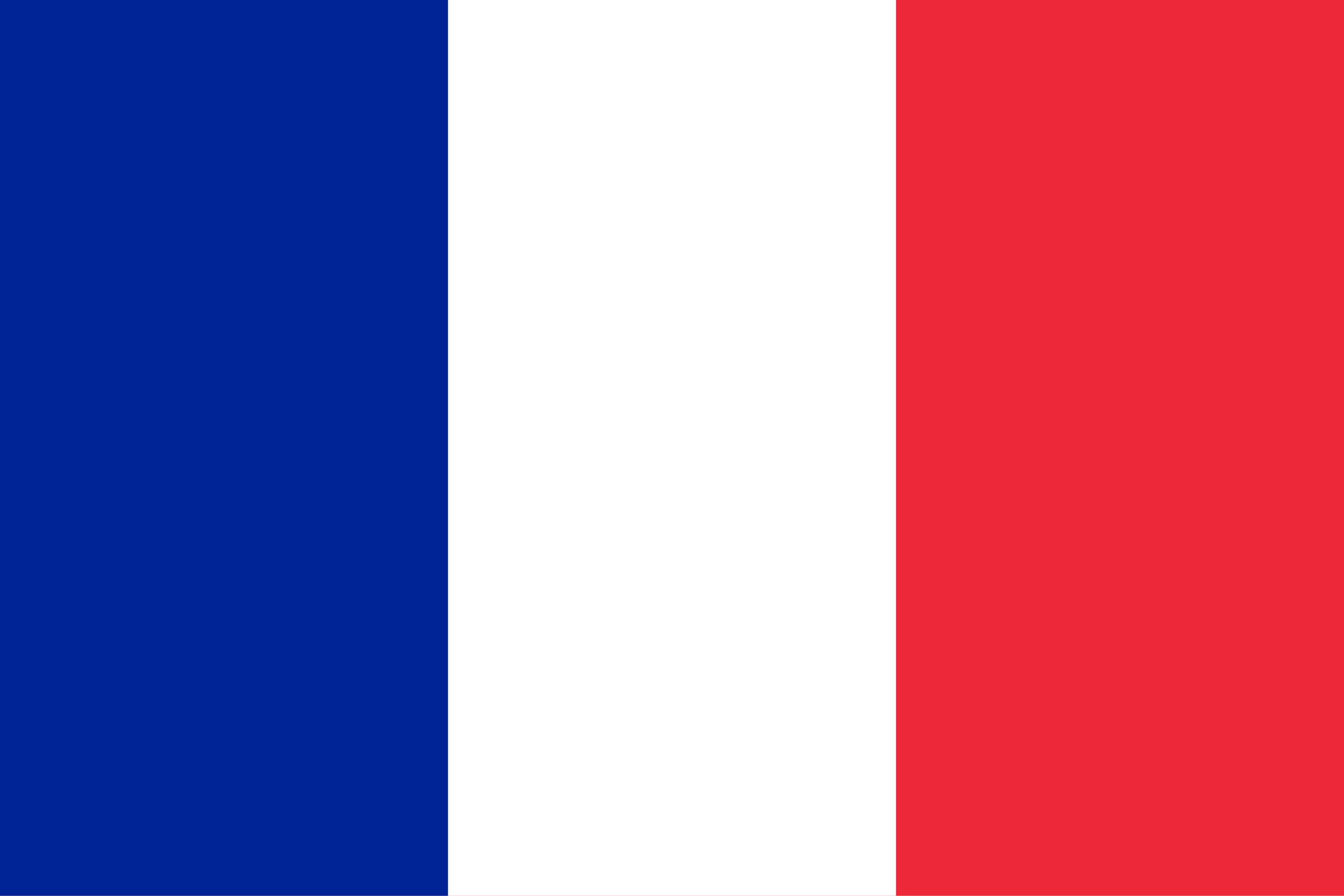六月末から七月初めにかけて実施されたフランス国民議会(下院)選挙で、マリーヌ・ルペン率いる「国民連合」が大躍進を果たした。だが日本の報道では、国民連合は「極右」のレッテルを貼られ、決選投票の結果「失速した」とも報じられた。
そうした報道は欧米メディアの無批判な受け売りであり、フランスの現状を正しく伝えていない。国民連合が支持を拡大し続けている理由を読み違えてはいけない。
今回、現代フランスの政治、社会状況に精通している堀茂樹・慶應義塾大学名誉教授に「『国民連合』現象の謎」について聞いた。
(編集部)
決選投票のマジック―左派と中道派による「国民連合」の封じ込め
国民連合(RN)の前身は、ジャン=マリー・ルペンが一九七二年に設立した党、「国民戦線」(FN)です。ルペンは七四年にさっそく大統領選挙に出馬しましたが、その折の彼の得票率はわずか〇・七四%。当時の彼の勢力は泡沫にすぎませんでした。
三十年後の二〇〇二年、ジャン=マリー・ルペンは大統領選挙の第一回投票で一六・八六%を獲得し、社会党の有力候補を退けて決選投票に進みました。そのこと自体がフランス社会を震撼させたのでしたが、決選投票では、対立候補となった保守のシラクの五分の一程度の票しか集められず、あえなく敗退しました。
しかしその後、ジャン=マリーの路線と決別して党の実権を握った娘マリーヌが二〇一七年の大統領選でエマニュエル・マクロンと対決し、約三四%の得票率を記録しました。さらに、党名を「国民連合」に変えたあとの二〇二二年の大統領選では、ふたたび決選投票でマクロンと相まみえ、敗れはしたものの全有権者の四一・五%の支持を得ました。
そして今回は国民議会(下院)選挙。国民連合は三週間前の欧州議会選挙での圧勝の余勢を駆って、マリーヌ・ルペンを大統領候補として温存しつつ、弱冠二九歳の精悍な党首ジョルダン・バルデラを表に押し立てるかたちで選挙戦に臨みました。第一回投票で国民連合がフランスの最大政党となる勢いを見せると、第二回投票(決選投票)の前に保守の共和党から一部が離れ、国民連合に合流しました。しかし結局、国民連合が得た議席数は一四三議席でした。下院議員の定数が五七七であることと考え合わせて、この数値をどう解釈すべきでしょうか。他党によって抑え込まれたのも事実ですが、堅調に勢力を拡大したともいえます。
これまでの下院選挙で国民連合が得た議席数を振り返りましょう。二〇一二年の選挙ではわずか二議席でした。前々回の二〇一七年に八議席まで増え、前回の二〇二二年には八九議席まで伸びました。そして下院解散にともなう今回の選挙では、一四三議席を得たわけです。この観点から見れば、国民連合は目覚ましく躍進したといえます。
しかし、事前の予想では手が届くかもしれないといわれていた下院の絶対過半数、二八九議席には遠く及びませんでした。なぜかというと、国民連合の党首が首相の座につくことを恐れた中道勢力と左派勢力が連携して大きな壁を造ったのです。この壁が「共和主義戦線」と呼ばれるもので、この戦線に国民連合以外の主要政党すべてが集結したため、国民連合は抑え込まれてしまいました。
フランスの下院選挙では小選挙区制ですが、第一回目の投票で投票総数の十二・五%以上を獲得した候補が決選投票に駒を進める権利を得ることになっています。
一回目の投票では、圧倒的多数である計二九七もの選挙区で国民連合の候補者が第一位となりました。第二位につけたのは、多くの場合、中道や左派の候補者でした。そんな状況の中で、首位の国民連合の候補者を負かすために二位・三位・四位以下が揃って「共和主義戦線」のスクラムを組み、二位の候補を押し上げたのです。
この「二回投票制度」は、一九五八年、第五共和制を創始したドゴールが、多数派形成を容易にして政治を安定させるべく導入した制度なのですが、この方式が今回、皮肉なことに、最大政党による多数派形成を阻む方向に機能したのです。
先頃英国でも総選挙が行われ、労働党が十五年ぶりに政権を奪取しています。英国の下院選挙は小選挙区制一回だけの投票です。フランスが同じ選挙制度であれば、国民連合は下院の絶対過半数を超え、首相の権限を手中にしていただろうと思われます。
最終的に、国民連合は得票率三七・三二%だったものの、議席は前述のように一四三にとどまりました。急進左翼から穏健左派までの連合体「新人民戦線」は二五・九%の得票率で一八二議席を得ました。マクロン大統領の中道連合も、得票率は二五・五六%なのに一六八議席を得ました。けっしてルール違反ではないのですが、理不尽だという印象は拭い難いですね。
国民連合の当選者の平均獲得票数は七万六〇八票でした。一方で、マクロン大統領派の当選者の平均得票は三万八五〇九票。「新人民戦線」の当選者のそれは三万七二七五票でした。当選した国民連合の候補者は一人々々、他党の当選者の約二倍の数の有権者に支持されていたのです。
「周縁部のフランス」が支持する「国民連合」
「国民連合」は全体で一千万を超える票を獲得し、この観点から見ても他党を引き離していました。投票率は一回目、二回目とも六六・七%とかなり高かったので、常日頃から百家争鳴のフランスの世論の中で、最も大きな民意の塊(かたまり)は「国民連合」を支持していたと言えましょう。
「国民連合」に投票した人の多くは、「票が盗まれた」かのような苦い後味を噛みしめているに違いありません。しかし不正があったわけではなく、すべて合法であり、定められたルールのメカニズムが働いた結果であるわけです。
人によって受け止め方はさまざまでしょうが、私としては、国民連合が政権を奪取するには、「いまひとつ…」という感じがなお大方の有権者に残っているのだろうと思います。昔と比べれば改善されていますが、「国民連合」の候補者の内には自民族至上主義的な言葉を平気で、あるいは迂闊に口にする「レイシスト」も何名か混ざっていて、公開の場でそれが指摘され、危険視されたこともあったようです。
開票終了後、党首ジョルダン・バルデラが、公認候補者の内に逸脱者がいたのは事実だ、もっと厳しく精選すべきだったと反省している、次回はその点をきっと改める、と述べていたのが印象的でした。バルデラやマリーヌ・ルペン本人は、国境管理の厳格化や移民流入の抑制を唱えていても、いささかも「レイシスト」などではありません。
また、今や一千万人を優に超える「ふつう」の生活者たちから支持されるようになった政党を安易に「ファシスト」呼ばわりするのは慎むべきだろうとも思います。ところが、日本の報道機関のほとんどは未だに「国民連合」を「極右」呼ばわりしています。「極右」はまるで合鍵のように濫用されている蔑称なので、これは悪しき「レッテル貼り」ですね。レッテルは現実を隠し、検証を排除し、議論を封殺してしまいます。
では、五〇年前にされた国民連合が、四半世紀前から加速度的に躍進してきたのはなぜか。政治情勢の推移の背景には必ず人口学的・社会学的な要因があるので、ここで一つ参考にすべきは、地理学者クリストフ・ギリュイの指摘です。ギリュイは本格的な学者ですが、大学教授ではなく、いわゆるアカデミアの外にいる人です。彼がかれこれ二十年前から提唱してきて、今やジャーナリズムにまで浸透したのが、「周縁部のフランス」という概念です。これは特定の地域と同時に、人口集団をも指す言葉です。
フランスの社会は、パリ、マルセイユ、リヨン、トゥールーズといった比較的富裕な都市と、移民系マイノリティの多い都市郊外と、そのさらに外に拡がる田園地帯で構成されています。人口分布におおきな偏りがありますから、田園部はまさにフランスの「周縁部」に相当します。そこには、総称で「コミューン」と呼ばれる市町村が数多く存在し、それぞれ市長、町長、村長の下、地方自治体を営んでいます。
「周縁部のフランス」を構成しているのは、比較的低学歴で、経済的にも中・下層の大衆、つまり庶民です。この人びとこそ、フランス国民全体の中でも、一九八〇年代からのグローバリゼーション――国境を超える欧州市場の統合、欧州単一通貨ユーロの採用、多くの工場の閉鎖や海外移転という形で現れた脱産業化、大量移民・難民の流入など――で特に「割を食った」層だということは、いまさら強調するまでもないでしょう。
伝統的には、この地域の社会は、主にカトリック教会のネットワークと、当時は有力政党だった共産党の生活ネットワークで構造化されていたのです。しかし、一九七〇年代を境に、脱宗教と脱革命イデオロギーという歴史的推移がその二つのネットワークを消失させました。そうして連帯の拠り所を失い、バラバラに分離されたこの地域の人びとの心に、改めてフランスのアイデンティティと誇りを語りかける「国民連合」のナショナリズムが浸透していったのは、ほとんど物理的ともいえる必然でした。今日、「周縁部のフランス」では、国民連合が圧倒的に支持され、選挙のたびに、ほとんどの選挙区でトップ当選しています。
ふだんは社会上層のメディアから無視され、「声なき大衆」にとどまっていることの多いこの人口集団「周縁部のフランス」がその存在を一躍際立たせた事件が、フランスの同時代史の中で二回ありました。
一つは、EUの連邦制的な性格を強める(=国家連合的性格を弱める)欧州憲法条約の批准を問うた二〇〇五年の国民投票です。左右対立を超えてエリート層や富裕層がこぞって批准を是認する「諾(ウイ)」に賛成し、容易に批准が成立するだろうと予測していたにもかかわらず、大々的な国民的討論の結果は、五五%の「否(ノン)」による批准の否決でした。「周縁部のフランス」がEUレベルの更なるグローバル化に反抗したのでした。
しかし、その三年後には、サルコジ政権下、欧州憲法条約の内容が「リスボン条約」と名前を変えただけで、国民投票を経ずに上下院合同の総会の場で批准されてしまいます。「民衆の勝利」が、EU統合自体を進歩と考える左右の代議士と上院議員たちによって掠め取られてしまったのです。フランスの庶民がエリート層に対して決定的な不信感を抱いたのはこの時だといわれています。
「周縁部のフランス」が姿を現したもう一つの実例は「黄色いベスト運動」です。二〇一八年から燃料価格高騰への反対デモをきっかけに起こり、すべての予想を上回る広範さと持続力を示した全国的大衆運動ですが、当初のかなり長い期間の参加者の多くは「周縁部のフランス」から出ていました。まる一年続いても政治的には結実しなかったあの前代未聞の運動は、まさに死に物狂いで展開された反グローバリゼーションの「藻掻き」だったといえましょう。
忘れてはならないことが二つあります。一つは、「黄色いベスト運動」の特徴は、「今まで一度もデモに参加したことがない」という「ふつう」の庶民が立ち上がった「デモ」であったことです。そしてもう一つは、参加者たちの総意といえる要求が、(大統領発議ではなく)国民発議の国民投票の法制化だったことです。実は、直接民主制の部分的導入によるリアルな国民主権の奪回こそ、「黄色いベスト運動」の根底にある悲願だったのです。
「周縁部のフランス」において現在顕著な国民連合の人気は、クリストフ・ギリュイの分析によれば、国民連合が周縁部の人びとを啓蒙した結果ではありません。むしろ、周縁部の人びとの声を聞いてくれる政党、その声を代表してくれる政党として、国民連合が――国民戦線時代に遡るさまざまな汚点や烙印にもかかわらず――選ばれたのです。「ふつうの庶民が自分たちで考え、自分たちで判断するところまで成熟しているのだ」と、ギリュイは評価しています。
グローバル化した社会におけるエリート層と庶民層の分断と変容を見るこの視点は、英国のジャーナリスト、デイヴィッド・グッドハートが、ブレグジット(英国のEU離脱)を念頭に置きつつ提示した「somewhere(何処か)の人びと」と「anywhere(何処でも)の人びと」の対立、「どこでも族」と「ここだけ族」の対立とも符合しています。
「somewhere」—特定の国のある地域に根ざして暮らす人びとに対して、「anywhere」—世界中どこでも暮らせる人びとという区分ですが、前者が庶民とすれば、後者は広義のエリートです。但し、「グローバルに活躍する人びと」などという言葉で称揚されるこのエリートもまた、実は都市部の環境の中にしか住んでいないわけで、この事実も見落とすわけにはいきません。、都市部と地方の間の不平等という日本でも顕著な現象と関係するポイントだからです。
フランスの政界は現在、三極に分化しています。弱体化したマクロン大統領を支える与党が中道、社会民主主義者と急進左翼が混ざり合っている「新人民戦線」が左派、そして国民連合と、より先鋭なナションリスト・グループ「再征服」が右派という構図です。
一方、社会学的・地理学的観点から見ると、先に述べたように、都市部、都市郊外、そして「周縁部のフランス」という、質的に異なる三つの部分に分かれています。国民の一体感を削ぐこの状況はデモクラシーを阻害します。
こうした危機的状況の中、どの様な政権が発足するのか、視界はまったく不透明です。マクロン大統領は現在、新首相の指名をパリ・オリンピック後に先延ばししてしまっています。
劣化する民主制――「国民」政党は日本でも生まれるのか
しかし、緊張感があるぶん、フランスはまだマシかもしれません。翻って日本を見ると、政治的には呆れ返るほかない状況が続いていますから。都知事選が終わったばかりですが、「民主主義は壊れている」と言うしかないですね。選挙序盤の「掲示板ジャック」なんてまさにその象徴でした。有力候補だった小池知事、蓮舫氏、また注目を浴びた石丸伸二氏にしても同じです。全く中身がない…。
都知事選の機会に一つ思い出したことがあります。今回、元航空幕僚長の田母神俊雄氏が立候補していました。田母神氏は二〇一四年の都知事選にも立候補しており、その折は六一万票を獲得して健闘しました。印象的だったのは、私の記憶が正しければという留保付きで申しますが、足立区、葛飾区、板橋区、江戸川区、北区など、東京の二三区内で比較すれば住民の所得水準があまり高くないと目される地域で、田母神氏の得票率がとても高かったことです。
当時、リベラル層が支持した候補は細川護熙元総理でしたが、彼はこれらの地域ではからきし票が取れていませんでした。細川氏は当時「脱原発」を唱え、小泉純一郎元総理と並んで選挙カーに乗り、多くの華やかな文化人の応援を得ていましたが、「脱成長」も込みになったその主張は、庶民層にはまったく響かなかったのです。因みに、今回の都知事選でも、蓮舫氏が優先的に演説したのは、渋谷や新宿など、「お洒落な街」「浮いた界隈」ばかりだったのではないでしょうか。
足立区、葛飾区、板橋区、江戸川区、北区などは、一般的に富裕な東京の二三区内では、どちらかといえば「周縁部」に当たる区です。だとすれば、「周縁部のフランス」で、かつては強かった既成の左派政党が拒否され、国民連合に支持が集まっているフランスの現象と、やや類推的な現実だといえるのではないでしょうか。
今回解説したフランスの下院選挙で、決選投票の結果、下院の第一会派を作ることになった左派連合の「新人民戦線」という名称は、第二次世界大戦前の一九三六年、ドイツで勃興していたナチズムに対抗する為に結成された「人民戦線」の名称のもじりです。当時は穏健右派ともいえる中道派から社会党からを経て共産党に到るまでの勢力が結集し、ユダヤ系の人道主義的社会主義者レオン・ブルムをリーダーとしていました。
彼らの支持母体は主に下層と中間層の有権者でしたから、本当の意味での「人民」の戦線だったのです。ところが、それにあやかって今回、国民連合に対抗する為に結成された「新人民戦線」の支持者たちはどこにいるか?「周縁部のフランス」に、「新人民戦線」の票田は殆どありません。労働者にも農民にもそっぽを向かれています。支持しているのは、都市のブルジョワジーと、都市郊外に住む移民系マイノリティなのです。大多数の「人民」の意思を代表しない左派とは何でしょうか。
他方、国民連合が躍進した根本の理由は、正統的なドゴール主義の勢力がほぼ消失したフランスにおいて、「ネイション(国民集団)」を価値として打ち出し、率直に愛国心を鼓舞した唯一の政党だということに尽きます。もともとはナチスに協力したヴィシー政権の系譜に連なる反ドゴール主義の勢力であった国民連合が、今このようなポジションに到っているのは皮肉でもあり、意味深いことでもあると思います。
国民連合が訴えているのは「国家主権」であり、「集団的アイデンティティ」の重要さです。これはさまざまな批判にもかかわらず、これを一定の限度の中で堅持することは、デモクラシーに必須の条件です。保守や左派が唱えてきた「開かれた社会」や「EU主義」は、ネイション(国民集団)を枠組みとしてしか成立しないデモクラシーを蝕み続けてきました。
左派政党は本来なら、まずは社会経済的な生活苦と闘う庶民の代弁者となるべきですが、彼らが重視したのは、あるいは少なくとも彼らが重視しているように見えたのは、フランス伝統の普遍主義に反する多文化主義による反レイシズム運動や、差異主義的価値観に立って個人の属性アイデンティティを擁護するLGBT運動などの社会文化的テーマでした。
日本の左派にも同様の傾向があります。枝野代表時代の立憲民主党の政策の一丁目一番地は、なんと「選択的夫婦別姓」でした。また、二〇一五年来、法政大学教授の山口二郎氏等を中心とする「市民連合」という団体が、野党共闘を取り持つ存在として動いています。しかし、彼らが唱えるのはいつも、多数派の暴走を止めようとするインテリ好みの立憲主義的テーマであって、基本的に多数派の意志を実現して行こうとする民主主義的テーマではありません。これでは、リアルな生活苦を乗り越えたがっている庶民の支持を得られる訳がありません。
野党共闘が今後も立憲民主党の緊縮派や市民連合に主導されるなら、庶民層から支持を得ることはあり得ないでしょう。それでは政権交代はできません。世界に脱グローバル化の時代が来ている今日、日本にも、率直に国民国家の再興を目指す政治集団を出現させるべきだと思います。
(著者プロフィール)
堀茂樹(ほり・しげき)氏
略歴昭和二七年滋賀県大津市生まれ。慶應義塾大学名誉教授。専門は二十世紀フランス思想を中心とする西洋思想史。二〇二二年度のノーベル文学賞に輝くことになったアニー・エルノーの作品を夙に日本に導入するなど、現代フランス文学の紹介者としても知られ、特にアゴタ・クリストフ『悪童日記』(早川書房)の翻訳は有名。最近の訳書には、人類学者エマニュエル・トッドの大著『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』(文藝春秋)、カロリーヌ・フレスト『「傷つきました」戦争』(中央公論新社)などがある